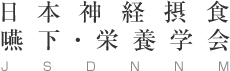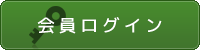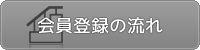加齢と摂食嚥下機能:京都長寿コホート研究の知見から(2025/08)
加齢に伴う摂食嚥下機能の低下は、高齢者の栄養状態だけでなく、服薬や日常生活活動にも関連していることが報告されています。我々は2017年より高齢者住民を対象としたコホート研究(高齢者を長期間にわたって追跡し、特定の要因(例:喫煙、食生活、環境要因)と疾病の発生との関連を調べる研究のことです)を実施しています。対象は京都北部(海の京都)の京丹後市および近隣に在住の約1,000人の高齢者の方々です。この地域は100歳以上の方(百寿者)の割合が全国平均の2.8倍となっており、本研究はこの長寿の秘密を探ろうというものです。
参加者は京丹後市立弥栄病院に来院していただき、血液検査、心臓超音波、CTを含む医学的評価、フレイル検診、日常生活調査を実施します。また、摂食・嚥下機能は反復唾液嚥下テスト(RSST)、水嚥下テスト(WST)、食物テスト(FT)、舌圧測定等で評価し、さらに生活・社会習慣(食習慣、口腔清掃、社会参加活動)との関連を横断的に分析しています。
舌圧は加齢とともに有意に低下しましたが、嚥下機能の簡易検査(WST、RSST、FT)との直接的な相関は認められませんでした。舌圧は歯磨き回数と正の関連を示し、また下肢筋力(膝屈曲筋力)とも関連しました。FTは間食頻度と関連し、WSTは社会参加活動時間や他者との交流時間と関連することが示唆されました。さらに、間食頻度は服薬困難および受動喫煙と関連し、食事時間は交流時間と関連していました。以上の結果より、舌の力を保っている方の多くは毎日の歯磨きを丁寧に行って、口の中を清潔に保つ習慣があること、外に出て人と会ったり地域の活動に参加したりする時間が多い人ほど水嚥下テストの結果が良い傾向にあることが示唆されました。
本研究の結果は、高齢者の摂食嚥下機能が生理的側面だけでなく社会的要因にも関連していることを示唆しています。加齢に伴う摂食・嚥下機能の状態は、摂食嚥下運動や栄養状態だけでなく、日常生活や社会的なウェルビーングにもかかわるものと考えられます。現在、私たちはこの研究の5年後の追跡調査を進めており、同じ参加者の方々がどのように変化しているのかを詳しく調べています。こうした長期的なデータの分析によって、食べる力や飲み込む力が長く保たれる秘訣をさらに明らかにし、皆さんが健康で元気に長生きできるように役立つ情報を今後も発信していきたいと考えています。
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科
臨床医学教育学、脳神経内科学
山脇 正永