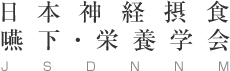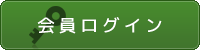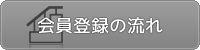気管切開術の安全な管理(2025/07)
かつて小生は気管切開術を当時卒後3年の先輩から教わった(見た)。教わったカニューレ交換法は「抜いて、そのまま入れる」だけ。気合いを要した。術式を教わったのは消化器外科医(当時卒後6年)からである。救急外来や外科病棟に住み着いていたレジデントがすぐに習得すべき「基本手技」であった。
2018年6月には日本医療安全調査機構から「医療事故の再発防止に向けた提言第4号、“気管切開術後早期の気管チューブ逸脱・迷入に係わる死亡事例の分析」が出された。同年、小生主宰の第14回日本神経筋疾患摂食嚥下栄養研究会では「気道・気管切開管理とトラブル予防」と題してシンポジウムを開き、翌年の本学会コラムでも話題にした。近年、看護の特定行為研修制度のなかに”気管カニューレの交換“があり、診療現場での教育、実習が始まっている。定められた手順書により交換手技を学ぶ。安全な管理と危険察知に非常に有効である。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は毎年の総会や秋期大会で、学生・研修医対象のハンズオンセミナーで気管切開術実習を継続している。日本気管食道科学会でも気管切開を題材とした教育企画が開催されている。2023年には外科的気道確保マニュアル第2版を出版した。この電子ブックには日本気管食道科学会の公式ホームページから無料でアクセスできる(https://www.kishoku.gr.jp/e-book/book-2/#page=1)が、Amazonからオンデマンド印刷でも入手可能である。(https://www.amazon.co.jp/dp/4991305918/)是非、手に取ってほしい。
しかし残念ながら、気管切開関連の事故は起き続けている。医療安全のマニュアルも、事故調査報告書も読まれなければ意味がない。ある基幹病院における気管切開術後の事故の相談をうけたが、気管切開術の手技には各種提言やマニュアルは反映されていなかった。根気よく伝え続けることが重要である。ただ、その事例における最大の問題点は、短頸・肥満患者における安全なカニューレが国内に存在しないことであった。有効長を調節できる気管切開カニューレは1種のみ存在するが、単管であるために痰がつまりやすい。現在では、オーダーメイドでサイズを決められるカニューレや若干有効長が長いタイプもやっと市販される様になった。メーカーの理解と協力も重要であると強く感じた。
愛知医科大学病院副院長、耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授
藤本保志