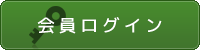第9回学術集会 京都大会 一般演題抄録集
「PAP 装着が有用であった治療抵抗性重症筋無力症の嚥下障害例」
関道子1)、森静香1)、辻中猛1)、荻野智雄1)、飯高玄1)、金原晴香1)、田原将行2)、
林隆太郎2)、冨田聡2)、大江田知子3)、舘村卓4)
1)国立病院機構宇多野病院リハビリテーション科
2)同神経内科
3)同臨床研究部
4)大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座
【症例】61 歳女性。2007 年構音障害、嚥下障害が出現、球麻痺が主体の抗AChR 抗体陽性重症筋無力症と診断。2008 年気管切開、胃瘻造設、人工呼吸器管理。嚥下造影(VF)では、経口摂取困難と評価された。
2009 年3 月継続治療及びリハビリ目的で当院入院。薬物療法・血液浄化療法(血漿交換)を継続的に施行。
ST 初期評価では挺舌範囲やや制限、舌尖挙上・軟口蓋挙上不可。反復唾液嚥下テストで30 秒間に4 回嚥
下が惹起したが、喉頭挙上距離はごく小さかった。VF では、口蓋帆咽頭(いわゆる鼻咽腔)閉鎖不全、咽
頭収縮不良、食道入口部開大不全にて食塊の咽頭通過に時間を要した。咽頭冷圧刺激法、メンデルゾーン手
技を用いた嚥下パターン訓練を中心に間接訓練実施。機能は血漿交換による改善と効果の減弱による増悪を
繰り返したが、嚥下時の喉頭挙上距離は徐々に改善した。2 ヶ月後に直接訓練開始。その後、シクロホスフ
ァミド・パルス、リツキシマブ投与。最大摂取量は5 ヶ月後に20 口、15 ヶ月後に40 口、31 ヶ月後に50
口に達したが、その時点をピークに嚥下機能は低下傾向となった。34ヶ月後に舌口蓋接触補助床(PAP)
を導入したところ、VF 上で「舌と口蓋の接触」「食塊形成」「咽頭への送り込み」の改善、「咽頭通過時間」の短縮をみとめ、経口摂取量は徐々に増加、41ヶ月後に約一食の摂取が可能になった。また、PAP の継続的な使用により、食事時間が60 分から25 分に短縮した。経過中、軟口蓋麻痺に変化なく、舌萎縮は進行したが、嚥下時の喉頭拳上距離は改善した状態を維持。頚部突出嚥下が習慣化した。
本例は薬物治療およびリハアプローチにより易疲労性の改善、喉頭拳上距離改善、食道入口部開大が得ら
れ、楽しみレベルの経口摂取が可能になった。さらにPAP 装着により易疲労性および咽頭への送り込みが改
善し、摂取量の増加・食事時間の短縮につながったと考えられた。
「縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーの食道入口部開大不全に対してバルーン拡張法を実施した一症例」
北村貴信1)砂田千賀子1)福原美樹1)輪島志保1)佐藤松子2)糟川歩2)千田圭二3)
1)独立行政法人国立病院機構岩手病院リハビリテーション科
2)独立行政法人国立病院機構岩手病院看護課
3)独立行政法人国立病院機構岩手病院神経内科
【症例】69歳、男性。32歳頃より歩行障害と両下肢のしびれが出現。56歳に縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)と診断。57歳より当院に通院、杖歩行であった。58歳、歩行器に移行。64歳、むせのため食形態を調整。66歳より通院で摂食嚥下訓練開始。67歳、這うか車椅子で移動。69歳にて気管支肺炎のため当院に入院となった。
肺炎治癒後にVFを実施したところ、嚥下障害の主因は食道入口部開大不全であり、梨状窩への食物の残
留も観察された。
【目的】ミオパチーに対するバルーン拡張法の既報として、筋ジストロフィーの食道入口部開大が改善した
報告例がある。本研究にて我々は、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーに対して摂食嚥下機能の向上を図る
ため、バルーン拡張法を実施、VFで再測定し効果を検討した。
【方法】1)バルーン拡張法:フォーリーカテーテルを25㎝挿入した。シリンジで空気を3~4ml注入しバル
ーンを拡張後、そのままカテーテルを引き抜いた(単純引き抜き法)。この操作を看護師が中心となって昼
食前に5回実施し、患者は昼食としてゼリー食を経口摂取した。摂食評価及び口腔ケアを主に言語聴覚士が
行った。2)VF:リクライニングシート角度60°にてバリウムゼラチンゼリー軟らか、硬めなど食形態のレ
ベルの低いものから経口摂取し、VF側面像を用いて摂食嚥下の動態を評価した。
【結果】VF:食道入口部最大前後径がバルーン拡張法の前後で1.9倍拡大し、輪状咽頭筋の弛緩がみられた。
それとともに咽頭残量が減少した。退院後の経過:自宅復帰後、主要な栄養は胃瘻より摂取しているが、昼
食前に一部介助でバルーン拡張法を行い、ゼリーレベルの食形態を昼夕食時に経口摂取している。
【結論】バルーン拡張法は、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーの進行期に認められた輪状咽頭筋の弛緩不
全に対して即時的に有効であった。
「筋強直性ジストロフィー患者とデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の嚥下圧の相違点について」
梅本丈二1)、古谷博和2)、笹ヶ迫直一2)、荒畑創2)、酒井光明3)、
喜久田利弘1)
1)岡大学医学部歯科口腔外科学講座
2)国立病院機構大牟田病院神経内科
3)国立病院機構大牟田病院リハビリテーション科
【目的】筋強直性ジストロフィー(DM1)は、特徴とされる咀嚼筋や頸部筋の筋力低下が
摂食・嚥下障害の原因となる。デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、筋力低下と
筋萎縮は徐々に進行し、年齢とともに嚥下障害も進行することが報告されている。両疾
患は、臨床的には類似した筋障害を認めるが、嚥下障害についてはかなりの相違がある。
そこで、今回DM1 とDMD 患者の嚥下障害の相違について、舌圧と嚥下圧測定から比較検
討した。
【方法】対象は、2012 年11 月以降に国立病院機構大牟田病院で嚥下造影検査(VF)を
行い、食形態スコアと舌圧測定値をマッチさせたDM1 男性患者7 名(平均年齢44.4 歳)
とDMD 男性患者(平均年齢22.6 歳)7 名である。食形態はスコア化し、常食を3 点、
軟飯食または粥食を2 点、ミキサーまたは流動食を1 点、経管栄養を0 点とした。舌圧
測定には口腔内バルーン式簡易測定装置を用いた。嚥下造影検査(VF)と嚥下圧検査を
同時に行い、ゼラチンゼリーと水分それぞれ約3ml を嚥下させ、咽頭残留物が全て通過
するまで複数回嚥下させた。嚥下圧測定は圧センサーを設置したカテーテルを食道入口
部まで挿入し、嚥下運動前後での下咽頭部と食道入口部の波形変化の最大値を解析した。
下咽頭部と食道入口部の圧変化について両群間の有意差と、各群において他の項目との
相関関係を検討した。
【結果と考察】下咽頭部と食道入口部の圧変化はいずれもDMD 群よりもDM1 群の方が低
かったが、有意差を認めたのは食道入口部の圧変化のみであった(p<0.01)。また、両
群とも水分嚥下時の食道入口部の波形変化の最大値と年齢の間に有意な相関関係を認
めたが(DMD 群:R=-0.811、p=0.04;DM1 群:R=-0.782、p=0.05)、他の項目間
の有意な相関関係は認めなかった。DMD とDM1 患者は年齢とともに嚥下時に食道入口部
が弛緩収縮しにくくなるが、同等の舌圧低下であっても、DMD よりもDM1 患者の方が著
明な食道入口部の運動障害を生じることが示唆された。(799 字)
「誤嚥性肺炎発症から3 ヶ月後に3食経口摂取に至った球脊髄性筋萎縮症の一例」
田中佳子1)、福岡達之1)、斎藤翔太1)、坪田巧美恵1)、野﨑園子2)、高岡俊雄3)、児玉典彦4)、道免和久4)
1)兵庫医科大学病院リハビリテーション部
2)兵庫医療大学リハビリテーション部
3)兵庫医科大学内科学神経・脳卒中科
4)兵庫医科大学リハビリテーション医学教室
【はじめに】球脊髄性筋萎縮症(SBMA)は緩徐進行性の下位運動ニューロン疾患であり、四肢の筋力低下および筋萎縮、球症状を主症状とする。進行すると嚥下障害や呼吸機能低下をきたすとされているが、嚥下障害の病態や訓練経過に関する報告は少ない。今回誤嚥性肺炎を発症し、重度嚥下機能低下を呈したSBMA の一例を経験したので報告する。
【症例】60 代男性。X-14 年SBMA と診断。X 年5 月誤嚥性肺炎発症し当院入院。2 病日後に呼吸状態悪化し人工呼吸器管理になった。10 病日後、気管切開術施行し呼吸器離脱後にST 介入開始。初回評価時、四肢の筋力低下と筋萎縮、呼吸機能低下、弛緩性構音障害を認め、ADL はFIM:18/126、全介助レベルであった。嚥下機能評価では口部顔面の運動障害、舌萎縮、線維束性攣縮、軟口蓋挙上不全を認め、口腔内および気管カニューレのカフ上に多量の唾液が貯留していた。RSST:1 回/30 秒、喉頭挙上量は不十分であった。
【訓練経過】唾液嚥下困難、嚥下関連筋の運動障害に対し、アイスマッサージによる唾液嚥下訓練と可動域
拡大訓練から開始した。30 病日後PEG。51 病日後スピーチカニューレに変更し、ブルーダイテスト実施後
に直接訓練を開始した。口部顔面、頸部筋の筋力低下に対しては筋疲労に注意しBorgscale を用いた低負
荷の筋力訓練(舌筋、頸部筋の等尺性運動)を実施した。79 病日後よりムース食開始。93 病日後に実施し
たVF 検査で少量の咽頭残留がみられたが誤嚥は認めず3 食経口摂取開始。嚥下筋の筋力改善に伴い、筋力
訓練は負荷量の漸増が可能であった。その後食事量・食形態を段階的に調整し、常食の3 食経口摂食が可能
となり他院転院した。
【考察】今回誤嚥性肺炎発症後のSBMA の一例に対し、全身状態に応じた比較的長期の嚥下訓練を行い経口
摂食が可能になった。筋疲労や過用に配慮した筋力トレーニングは、SBMA の廃用に伴う嚥下機能低下に対
して有効である可能性がある。
「神経線維腫症2 型(NF2)の嚥下障害」
大山治朗1)久野隆道2)
1)小郡弥生訪問看護ステーション
2)白十字病院言語聴覚療法科
【はじめに】神経線維腫症2 型(以下,NF2)は,両側聴神経腫瘍を特徴とする常染色体優性の遺伝性疾患である.1/35,000~40,000 人の割合で発症する非常に稀な疾患であり,嚥下障害の症状や経過の報告は少ない.
【症例】30 歳代女性(発症時10 歳代後半).平成11 年,耳鳴りにて発症し両側聴神経腫瘍と診断,左側の腫瘍摘出.その後,徐々に腫瘍増大し両側難聴,左顔面神経麻痺,左小脳失調症,嚥下障害が出現.平成18 年,右側腫瘍摘出.平成19 年,呼吸状態悪化し気管切開と胃瘻造設,再度腫瘍摘出.平成22 年,4 度目の摘出術施行.
【評価】両側失聴,左眼失明,右眼も視力低下.意識は清明で認知面の低下なし.コミュニケーションは筆談や手話で可能.
顔面知覚,舌の前2/3 の知覚共に右側の低下.咀嚼筋は筋力低下著明(三叉神経).口唇を含む顔面の運動は困難(顔面神経).舌の後1/3 の知覚,咽頭および軟口蓋知覚は全て右側の低下(舌咽神経).軟口蓋挙上は乏しいが,カフ脱気時に発声は可能(迷走神経).舌の全体的萎縮はあるも運動は可能(舌下神経).反復唾液飲みテスト(以下,RSST):1 回.努力性だが何とか嚥下反射惹起.藤島の摂食嚥下Gr.3(条件が整えば誤嚥は減り,摂食訓練が可能).
【経過】舌運動は比較的すぐに改善したが、顔面神経の改善は認めなかった.10 分間程度はスピーチバルブの装着が可能となったが,カニューレの変更には至らなかった.正しい嚥下や舌運動,代償的嚥下法の獲得を目的に訓練を行い,6 か月後にはRSST が2 回可能となる.味覚刺激程度ではあるが本人の好きなコーヒーを摂取するに至り,正月にはお雑煮の汁も摂取された.しかし,それ以上の拡大は図れていない.
【おわりに】今回NF2 により嚥下障害を生じた症例の評価および訓練経過を報告した.NF2 の嚥下障害に対しては,脳神経損傷により回復が困難な機能と,回復の望める機能との見極めが必要であった.認知面の低下はなく,代償方法の習得が可能であった.
「重症心身障害児・者に関わる職種での摂食機能療法のイメージに影響する因子
-形容詞尺度、経験年数、言語聴覚士と看護師との関連-」
野々 篤志1)西村 愛美1)小倉 英郎2)伊澤 幸洋3)大塚 義顕4)
1)国立病院機構高知病院 リハビリテーション科
2)国立病院機構高知病院 小児科
3)福山市立大学 教育学部
4)国立病院機構千葉東病院 歯科摂食嚥下リハビリテーション科
【はじめに】現在、重症心身障害児・者(以下,重症児・者)の摂食・嚥下機能に対するリハビリテ
ーションや摂食機能療法の領域は成熟していると言い難い側面がある。今回、重症児・者に対して、
摂食機能療法を算定できる言語聴覚士(以下,ST)と看護師(以下,Ns)に対し、ポジティブに取り組
むことのできることを目的とし、摂食機能療法のイメージについて評定した。
【方法】
1)小林ら(2004)の先行研究を参考に、摂食機能療法に関連するイメージの形容詞尺度を作成し、2011 年11 月~2012 年2 月の間にSD 法で調査を開始した。2)ST(n=29)とNs(n=47)が評価した5 段階評定にける各平均値より主因子法で因子分析を行い、ST とNs の職種2 群間で摂食機能療法のイメージの平均値と有意差を求めた。3)摂食機能療法のイメージに関連する変数を決定する目的で、重症児・者に関わるST およびNs の各経験年数を従属変数、形容詞尺度30 項目を独立変数とする強制投入法による重回帰分析を行って各職域での要因を検討した。
【結果】
1)30 項目の形容詞尺度を評価したST(3.29±1.03 点,α=0.720)とNs(3.56±0.93 点,α=0.855)の職種2 群間で、「信頼できない-信頼できる」(p<0.0001)、「未熟-熟練」(p<0.0001)、「消極的-積極的」(p<0.0001)、「親しみにくい-親しみやすい」(p<0.001)、「依存-自立」(p<0.002)、「優先しない-優先する」(p<0.005)が有意差を認めた。2)摂食機能療法のイメージに関連する因子の形容詞尺度は、ST が「非日常的-日常的」(p<0.0001)、「堅苦しい-柔軟」(p<0.001)、R2=100%で、Ns が「優先されない-優先する」(p<0.006)、「不必要-必要」(p<0.015)でR2=82.2%であった。
【考察】ST とNs の摂食機能療法のイメージは、後者がポジィティブなイメージ寄りで、職種間での偏りを認めたが、イメージを共有できる職種間であった。また、ST は求められる水準やリスクの高さによって生じる専門職としてのストレスが、Ns は難易度の高い事例の評価や訓練の効果検証などを含めた質的変化がイメージに影響すると考えた。今後、指導者および現任者の養成が重要である。
「呼気筋力強化訓練を行い嚥下機能に改善がみられたパーキンソン病の一例」
金原晴香1)、関 道子1)、森 静香1)、辻中 猛1)、荻野 智雄1)、飯高 玄1)、植田 能茂1)高坂 雅之2)、冨田 聡2)、大江田 知子2)
国立病院機構宇多野病院リハビリテーション科1)神経内科・臨床研究部2)
【背景】
近年、種々の神経筋疾患、高齢者において、呼気筋力強化訓練によって呼吸筋や発声、嚥下に関わる咽喉頭の筋力が増強されることにより、呼気圧や咳嗽能力、嚥下機能が改善したとの報告がある。特にパーキンソン病患者に対しては、嚥下造影検査(VF)において食塊の喉頭侵入や誤嚥の所見が有意に改善したとする海外の報告があるが、本邦での報告はみられない。
【目的】
パーキンソン病1 例に呼気筋力強化訓練を行い、嚥下障害に対するその有効性について検討した。
【症例】
71 歳男性。4 年前に左手の振戦で発症。レボドパ治療により症状改善がみられパーキンソン病と診断された。今回、液体の飲み込みにくさを主訴に入院。ヤール重症度2 度。MMSE30 点。発話では、音声障害(G1R1B0A1S0)、軽度の声量低下に加えて、湿性嗄声を認めた。舌・軟口蓋の明らかな運動障害は認めないが、咽頭反射は消失していた。嚥下スクリーニング評価ではRSST5 回/30 秒、MWST プロフィール5。食事は米飯・軟菜食を摂取していた。
【方法】
フィリップス・レスピロニクス社製の吸気筋トレーニング機器threshold IMT を用いて呼気筋力強化訓練を行った。5 回の深呼吸を1 サイクルとして、10 サイクルを1 回の訓練とし、1 日3 回の訓練を4 週間行った。訓練施行期間中は、内服薬剤の調整及びST による機能訓練は行わなかった。VF 検査所見および舌骨移動距離、日本語版SWAL-QOL スケールを主要評価項目とした。
【結果】
VF 検査では、液体嚥下時の誤嚥が訓練前にみられたが、訓練後にはなくなった。ゼリー嚥下時に多量にみられた咽頭残留が、訓練後には明らかに減少していた。舌骨移動距離は6㎜から10mm と拡大していたSWAL-QOL スケールでは、特に「食事にかかる時間」と「疲労」の項目に改善がみられた。
【結論】
本症例において、呼気筋力強化訓練前後で嚥下機能の改善が示され、有効であったと考えられた。
輪状咽頭筋切断術を施行した眼咽頭筋ジストロフィーの一例
藤本保志、渡辺宏久*、加藤健、小澤喜久子、丸尾貴志、鈴木淳志、中島務
名古屋大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科
*名古屋大学大学院医学系研究科神経内科
(症例)61 歳男性。X-7 年(54 歳)に眼瞼下垂が出現、咽頭違和感と嚥下困難感が出現した。58 歳時までに複数の医療機関受診し原因不明とされ経過観察ののちに前病院神経内科にて筋生検等をうけ、眼咽頭筋ジストロフィー(以下、OPMD)と診断をうけた。その後は前医での嚥下訓練にて改善なく、X 年(61歳)嚥下改善目的に当科を紹介受診。
(既往歴)斜視、変形性脊椎症
(家族歴)同病の確定診断はないが母親が眼瞼下垂と嚥下障害、兄が眼瞼下垂。
(初診時所見)初診時、両側眼瞼下垂、開鼻声を認めた。四肢・体幹筋には筋萎縮・筋力低下は認めなかった。嚥下内視鏡では多量の下咽頭唾液貯留がみられ、嚥下造影では鼻咽腔閉鎖不全、舌根後方運動減弱、咽頭クリアランスの低下などを認めたが喉頭挙上は良好であった。前医での訓練中には一時期、鼻咽腔閉鎖改善を目的に補綴治療がなされていたが自覚的な効果に乏しく、当科初診時には抜歯等の影響もあり補綴使用が困難となっていた。また、頸椎前縦靱帯骨化症、変形性脊椎症があり骨棘が咽頭を圧排する所見も認めた。
(治療)X 年11 月、右輪状咽頭筋切断術施行。術後右反回神経麻痺を認めたが回復し、咽頭クリアランス改善し、食事時間短縮し食欲が増進、術後3 ヶ月で体重増加した。
(考察)OPMD は緩徐に進行する。Fradet によれば輪状咽頭筋切断術は有効であるものの長期経過をみると再増悪すると報告されているが、そのメカニズムについては詳述されていない。本例では手術後3 年を経て嚥下について経過良好で、臨床症状も検査所見も著変はない。OPMD の嚥下障害の要因は鼻咽腔閉鎖不全、咽頭収縮力減弱と考えられ、輪状咽頭筋切断術は咽頭の出口の圧を低下させて咽頭クリアランスを改善し、その病態に対応できた。一方、鼻咽腔閉鎖や頸椎骨棘に対しては直接外科的処置を講じていない。将来の増悪時には病態の変化にあわせた対応を準備する。
神経・筋疾患における誤嚥防止術の位置づけとは?
津田豪太1) 、清水良憲1)、田中妙子1)、中西庸介1)、高嶋絵里2)、里千鶴2)、谷口薫平2)、西本昌晃2)、端千づる3)、北村綾3)、細田暢子4)、川端登代美4)、木下充子5)
1) 福井県済生会病院 耳鼻咽喉科・頚部外科
2)同 リハビリテーションセンター
3)同 看護部
4)同 口腔外科
5)同 栄養部
摂食・嚥下機能の可逆性が失われた重症例に対する外科的治療として誤嚥防止術が施行されることが多い。誤嚥防止術は口腔機能が維持されていれば術後も約4 割の症例で経口摂取自立可能であり、肺炎の反復など生命を脅かす合併症を回避する役割は十分果たす治療手段である。ただ、いくつかの手術手技が報告されているが、適応がはっきりしていない気がする。特に、臨床経過の長い神経・筋疾患では、どのタイミングでどのような外科的介入をすべきなのかはっきりしない部分が多い。自験例でも誤嚥防止術の原疾患としては神経・筋疾患が最も多いがそれでも19 例に過ぎず(55 例中34.5%)、術式も過去の手術方法も含めると7 通りの選択がされていた。当科では原疾患の生命予後・発声機能と意思伝達手段・全身状態(栄養状態)・肺炎反復の有無・全身麻酔の可否・抗凝固剤の使用と休薬・解剖的な喉頭下垂の有無とその程度・カニューレや人工呼吸器の装着の有無などの項目を評価しながら術式は決定しているが、果たしてそれで十分なのであろうか。当院にも神経内科医が常勤し、症例の相談を受けることはあるが、手術症例のほとんどは県内外の施設からの紹介であり、情報量が不十分であったり、家族からの思い込みのような治療希望であったりすることも当惑する原因となる。また、同じ疾患であっても紹介される施設によってそのタイミングに一定の傾向がないことも外科医としては悩ましい。神経内科主体の本研究会で何らかの指導がいただけることを期待して当科症例のまとめを報告する。
『住宅型有料老人ホームにおける往診嚥下内視鏡の意義』
大宮貴明1)2)、吉田祥子3)、庄司仁孝4)、三串伸哉5)、湯浅龍彦1)
1)鎌ヶ谷総合病院千葉神経難病医療センター
2)難病ケアハウス仁看護ステーション
3)吉野内科・神経内科医院
4)東京医科歯科大学・医歯学総合研究科
5)東京医科歯科大学大学院・高齢者歯講座
【背景・目的】神経筋疾患は他疾患と比較し、医療・介護依存度が高いため自宅退院が難しく施設入所を余儀なくされる場合が少なくない。このような、施設療養となった場合の経口摂取については、前施設からの食形態が参考にされ、加えて介助者の経験等によって判断がされる場合が多い。嚥下内視鏡(VE)は大掛かりな設備が不要であり、療養先施設内へ持ち込みも容易である。今回一般療養先において、VE による食材・食形態を含めた嚥下機能検査を実施し評価を行い有用性の検討をした。
【対象・方法】神経筋疾患患者を積極的に受け入れている住宅型有料老人ホームに入所中の患者17 名(ALS:7、MSA:3、SCD:1、PD:1、AD:1、その他:4)を対象に、往診によるVE 検査を任意で実施。施設で提供している食形態を5 段階(常食・粗刻み・極刻み・ミキサー・楽しみ)および経口摂取困難に分類し、介入前後での食形態の変化を比較・検討した。
【結果】対象患者17 名中、食形態上昇10 名・不変6 名・低下1 名であった。段階別では、3 段階の上昇1 名(AD)、2 段階の上昇3 名(ALS:2、PD:1)、1 段階の上昇6 名(MSA:3、ALS:1、その他:2)、1 段階の低下1 名(ALS)の変化を認めた。また、全面的経管栄養から、何らかの経口摂取が可能となった患者は4 名(ALS・MSA・PD・AD)であった。
【考察】専門職種不在の施設では、嚥下機能検査・評価が難しく新たに病院の外来受診も現実的でないことが少なくない。また、安全性を優先するあまり経口摂取を躊躇してしまい往診医・介助者の経験のみで判断をすることが考えられる。今回、判断材料の一つとしてVE 検査を実施したことにより、神経筋疾患患者においても何らかの経口摂取開始や食形態の上昇を認める例が多くみられた。このことはQOL 向上につながると共に安全・安心に経口摂取を行うためにも重要である。以上、往診VE 検査は施設における嚥下の評価や食形態の決定などに極めて有力な方法である。