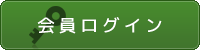国立療養所刀根山病院神経内科,国立療養所高松病院神経内科
野崎園子,市原典子
全国療養所神経内科(湯浅班班員)に摂食・嚥下障害についてのアンケートをおこない,33施設から回答を得た.ALSについて:対策は摂食・嚥下障害の症状が出てからおこなう施設が55%であった.また,PEG造設における合併症が5%以上である施設が全体の42%であり,内訳として呼吸不全や腹膜炎など重篤なものもあった.摂食・嚥下障害に対する施設の取り組みについて:評価は33%の施設で,訓練は直接訓練67%,間接訓練49%,嚥下困難食は78%の施設で実施されていた.経鼻経管栄養の対象はALS,SCD,PSP,PDの順に,PEGの対象はALS,PSP,SCD,PDの順に,誤嚥性肺炎の発生はSCD,PD,ALS,PSPの順に多かった.誤嚥対策としては,気管切開は57%,気管食道分離術は3%の施設でおこなわれていた.地域医療との連携では多職種の摂食・嚥下障害対策への参加を望む声が多く,病院と同様の評価,訓練,食事対策,経管栄養管理が地域医療の中で継続できないという問題点が挙げられた.医療環境としては,摂食・嚥下障害対策への診療報酬が低いこと,嚥下機能評価・訓練体制の整備,他科との連携などに問題点が指摘された.
国立療養所宇多野病院
古澤典代,姫田菜穂子,高橋政次(栄養士),小西哲朗(医師)
神経,筋疾患患者に発生してくる摂食・嚥下障害への対応は栄養管理をする上で当然のことと認識しているが個々によって異なり困難を擁す.平成11年より神経筋難病の基幹病院と位置づけられ,それと同時に嚥下委員会も設置され活動している.近畿管内七施設の調査ではパーキンソンが一番多いとの結果でその中で嚥下困難は47%でした.栄養士は食べやすい食事の工夫とともに増粘剤や補助食品を有効に利用し不足分は補助栄養で補い安全で嗜好に合った食事の提供に努めています.嚥下食の基準は?訓練食(ゼリー食)・?嚥下困難食1・2・3を提供し間接訓練,嚥下造影検査も実施し委員会で評価しその情報は院内ranも利用し共有をしている. 摂食・嚥下障害は医師,看護師,栄養士,調理師,家族など,ともっともチーム医療でなくてはできない治療であり積極的に連携を取るべきである.
国立精神・神経センター武蔵病院リハビリテーション科
及川奈美,伊東亜希子,松田高子,大矢 寧,山口 明
【はじめに】筋強直性ジストロフィー(以下MyD)患者の嚥下障害は,頻度が高い.しかしMyDは病識低下に加え「自主性低下,無関心,非活動」という特徴もあり,効果的な訓練は確立されていない.今回我々は嚥下障害のあるMyd患者に対して一般的な間接訓練を長期間行ったことを経過報告する.
【対象】ビデオ嚥下造影検査(Videoflurography,以下VF)で嚥下障害ありと認められたMyd2例.1例は57歳男性.運動機能はMydの障害度分類にてStage7.VFにおいて水状の造影剤は咽頭への侵入が認められ,泥状とヨーグルト状の造影剤は喉頭蓋谷と梨状窩に残留しつづける.1例は54歳男性.Stage7.VFは症例1と同じであった.2例とも嚥下障害の認識はあるが深刻さはなかった.
【方法】2例に対し嚥下障害があることを説明,訓練の必要性を納得してもらった.そして平均週4回,間接訓練を行った.判定は1ヵ月,8ヵ月,12ヶ月後3回.以下の項目で行った.1,自覚症状 2,他覚症状 3,VF評価
【結果】1,2症例共,間接訓練を継続出来た.2,自覚症状,他覚症状について1ヵ月後は変化なし.8ヵ月後,症例1,2共改善傾向であった.12ヶ月後は維持されていた.3,VF評価で12ヶ月間著明な改善は見られなかった.
【考察】嚥下障害のあるMyd患者が,間接訓練を継続できたのは,訓練の必要性を理解したことが要因だと思われる.以上により嚥下に対する長期の間接訓練は維持として有用性があると考えられた.
国立精神・神経センター武蔵病院リハビリテーション科,*セコム(株)開発センター
山口 明,日野 創,千葉 有,黒岩貞枝,及川奈美,伊東亜希子,松田高子,*石井純夫
【目的】食事介助を要する障害者に対し,食事動作の自立,更に食事を楽しむことへの支援装置を開発することは意義深い.そこで,われわれは摂食動作を介助する「食事ロボット」を開発,臨床的応用を試みた.
【対象と方法】対象は頚髄損傷,ギランバレー症候群(G-BS),筋ジストロフィー症(PMD),運動ニューロン疾患(MND),脳血管障害(橋出血),脊髄小脳変性症(SCD),パーキンソン氏病(P-D),脳性麻痺など11例を対象とした.年齢:22~62才,平均 51才,摂食は筋ジス例を除き要介助で,嚥下は気管食道分離術済みの橋出血例を含めて目下問題はない.方法は先ず「食事支援ロボット」(電動製)をセコム社開発センターと協同開発した.本装置はアームを中心とする本体部分,アーム先のスープン構造部分,食物を盛る器部分,さらに,使用者が操作するジョイスティック等の部分から出来ている.検討事項は①食物形態,②ジョイスティックの操作性,③食物の迎え込み(摂食の姿勢など),④QOL上の問題,⑤改良点の検討,などである.
【結果】①固形食に加え,麺類やペースト食でもスプーントフォークの改良により把持能力が向上した.②操作系を簡素化,半自動,自動モードにより手の振戦,知的障害を伴うような例でも適応とすることができた.③スプーン部分の改良により最初の設定で同じ位置に食物を運ぶようにしてあり,軽く唇を触れると食物が取り込み易いようにすることができた.筋ジス例などでは前傾による従来の食事姿勢が本装置により,姿勢の改善をみた.④自分の好きな時に食べたい物を自分のペースで食べれる.家族と向き合って食事が可能といった要介助時代とは数段異なるQOLの向上が得られた.
【結語】摂食が要介助の神経筋疾患11例について食事支援ロボットを用いた検討を行った.臨床的には頚髄損傷例が最もよい適応と考えられるが,他の疾患でも一定の効果をみた.SCDやP-D,知的障害例では操作の簡便化などが要求された.
国立療養所西鳥取病院神経内科
金藤大三,野村哲志,岡田浩子,井上一彦,下田光太郎,言語療法士 横田嘉子,伊藤有紀
食道入口部開大不全による嚥下障害患者に対する嚥下訓練としてバルーンカテーテル訓練法(以下バルーン法)がある.
今回我々はVF(ビデオ嚥下造影検査)にて食道入口部開大不全が認められた嚥下障害患者で代償法では回復が不十分な三症例にバルーン法を行った.バルーンは球状バルーン(16F膀胱留置カテーテル)を用い,手技としては単純引き抜き法と間歇空気拡張法,嚥下同期引き抜き法を使用した.空気は5ー10?,1回ごとの引き抜き回数は10回程度として1日1ー2回言語訓練士が行った.症例はすべてバルーン拡張時に不整脈がでないことを心電図モニターで前もって確かめた.またすべての症例で本方法以外の必要と思われる機能訓練を併用した.
症例1:72才 男性.下顎扁平上皮癌術後.67才時扁平上皮癌にて左頬粘膜から下顎骨を含め腫瘍切除及び下顎再建,放射線照射を行い,その後に嚥下障害を生じた.左下顎の変形と,左半側舌萎縮があり,嚥下動作前の咽頭流入と食道入口部開大不全による喉頭蓋谷や梨状窩の食塊の残留が非常に多かった.球状バルーンによる間歇的空気拡張法と単純バルーン引き抜き法を1日2回行い,嚥下は改善し,食事時間は1/3に短縮した.
症例2:51才 男性.Kearns-Sayre症候群.34才難聴.35才Kearns-Sayre症候群と診断される.44才両眼瞼下垂あり.四肢筋力が徐々に低下し,50才気管切開,人工呼吸器管理となる.両眼瞼下垂,眼球運動は全方向に軽度障害,嚥下障害,四肢筋の筋萎縮と脱力がある.嚥下時の誤嚥,食道入口部開大不全による喉頭蓋谷や梨状窩の食塊の残留があり,球状バルーンによる間歇的空気拡張法と単純バルーン引き抜き法を毎日1回行い,嚥下が改善した.
症例3:79才 女性.Wallenberg症候群.高血圧で2ー3年前より服薬中,めまいと嘔吐で発症し,嚥下性肺炎となる.右Horner徴候,嚥下障害右顔面,左半身の温痛覚障害,右半身運動失調があり,MRI検査で右延髄外側に梗塞巣を認めた.食道入口部開大不全,喉頭挙上不全があり,球状バルーンによる間歇的空気拡張法と単純バルーン引き抜き法,嚥下同期引き抜き法を行い,次第に柔らかい物なら食べられるようになった.
食塊が食道入口部を長期間通過しないと輪状咽頭筋部が筋拘縮など伸縮性低下を生じる可能性がある.バルーン法は伸縮性の低下した輪状咽頭筋部に対し他動的に伸展を繰り返し伸縮性を回復させると考えられる.このため術後の瘢痕性狭窄や筋疾患,放射線治療後の伸縮性低下にもWallenberg症候群と同様に改善効果があると思われた.
国立精神神経センター武蔵病院リハビリテーション科
千葉 有 永江順子 日野 創 山口 明
症例は,くも膜下出血(右MCA域)術後の60歳の女性で,嚥下障害のため喉頭気管分離術施行.術後,通常ならばリリース手術を行うことなしには不可能なはずの発語が可能となり,その後徐々に発語量は増加した.2002年5月初診時,発声の持続時間は1秒程度で,音声は概ね明瞭であったが,は行の声門摩擦音等の苦手な音もあった.鼻咽頭ファイバー及び透視により,吻合部付近の食道に貯留する空気の,喉頭からの流入・排出による,喉頭による発声と考えられた.訓練は,胸郭の動きにあわせて起こる空気の流入・排出を強化すべく,呼吸筋群の強化訓練を行った.また喉頭周囲の過緊張・過収縮が疑われたため,よりリラックスして発声する訓練と喉頭調節の訓練を行った.結果,同年9月には,発声の持続時間も3秒程度に伸び,声質も改善し,は行の声門摩擦音も発音可能となり,ピッチを変化させることも可能となった.喉頭気管分離術術後にリリース手術を行うことなく喉頭発声を行い,その能力を拡大できる可能性がある.
国立精神・神経センター国府台病院 神経内科
根本英明,木村暁夫,山田滋雄,吉野 英,西宮 仁,湯浅龍彦
症例は59歳女性.50歳左手のふるえ,固縮,歩行時腕振の減少で発症のPD.当初,trihexyphenidyl,levodopa/benserazide著効.56歳頃wearing-off,dyskinesia,dystoniaが出現.selegiline,cabergoline使用するも効果なかった.2001年12月13日,パーキンソン症状の悪化があり,入院.levodopa/benserazide増量(400mg→500mg)に伴いパーキンソン症状は改善した.しかし,幻覚・妄想が出現し,risperidone0.5mgを開始.4日後には両側声帯dystoniaのため正中固定.挿管・気管切開術を必要とした.嚥下障害も増強した.その後,四肢はrigo-spasticとなったが徐々に改善.ところが,6ヶ月経過しても声帯の正中固定と嚥下障害は改善しなかった.声帯の正中固定・嚥下障害はrisperidoneによるdystoniaと考えた.PDにrisperidoneを使用するのは慎重でなければならない.
国立精神・神経センター国府台病院 1)神経内科,2)放射線診療部
湯浅龍彦1)2),加藤融2),桜井淳2),黒崎栄治2),鈴木剛志2)
正常ボランティアが水を嚥下する時に得られた脳の機能局在を呈示した.
MRI装置は,1.5T MAGNETOM Symphony,被験者の口にチューブをくわえさせ,0.4 ml/secの流量で12ml注入し,嚥下させた.
fMRIは,グラディエントエコーによるEPI法で,55スライスの横断像で全脳(voxel size 3.6×3.6×3.0 mm)を撮像した.脳賦活部位を共通の脳座標に集約するために,EPI画像と同一のスライス位置で撮像したT1強調画像(voxel size 1.0×0.9×3.0 mm)とMPRAGE法の高分解能3D画像(voxel size 0.9×0.9×1.5 mm)を使用した.
結果:今回の飲水嚥下に関連して賦活された脳の機能活性部位を機能別に分類すると以下のようであった.(1)口腔や食道からの感覚系の求心路に関連するものとして,両側視床,両側後中心回がある.そして(2)随意的な咀嚼・嚥下運動に関連する運動系遠心路として,(右)前中心回,(右)内包,(3)咀嚼・嚥下運動の統合系としての補足運動野,左右の弁蓋部,(4)辺縁系の構造として右海馬,左前島回,帯状回,(5)制御機構としての小脳系(右小脳歯状核と右優位の左右の小脳半球)と大脳基底核(左右の被殻と左淡蒼球外節),それに加えて(6)視覚系の左烏距溝であった.
嚥下造影(VF)の実際
国立療養所高松病院神経内科
市原典子
当院においては,神経内科医を中心として,脳卒中内科医,耳鼻咽喉科医,言語聴覚士,栄養士,看護師で嚥下チームをつくり,嚥下障害の評価および治療にあたっている.嚥下障害をきたした患者にはまず,脳神経系の神経学的所見,嚥下障害に関する問診をとったうえでvideofluorography(VF)を行っている.問診では現在の食事形態,食事中のむせ,咳嗽・喀痰・嚥下困難・咽頭残留感・湿声の有無,食事時間・食事内容・摂取方法の変化,感染徴候をチェックする.VFは,造影剤を加えた模擬食品の嚥下過程をX線透視装置で撮影し,ビデオテープに収録することにより,嚥下の各相の評価をおこなうものである.造影剤は誤嚥した際の安全のために血管造影剤のイオパミドールを使用しており,保険外適応であるため承諾書をとっている.模擬食品はコーヒーゼリー,カルピスなどにほぼ同量の造影剤を混ぜて作っている.検査には座高や角度の調節が可能なVF専用チェアーを使用している.観察項目は,口腔期では嚥下開始の遅れ,口唇からのこぼれ,指示前の咽頭流入,食塊形成不全,奥舌への移動不良,口腔内の残留.咽頭期では嚥下反射の遅延,喉頭挙上不全,鼻咽腔閉鎖不全,喉頭侵入,誤嚥,咽頭クリアランス食道入口部開大不全である.
また,操作室ではビデオからのアナログ信号をメディアコンバーターでデジタル信号に変換し,同時にパソコンに取込みをおこない,時相解析に使用している.時相解析を用いて,ALS9名と健常コントロール9名の比較検討(未発表),PSP8名,PD8名,健常高齢者10名の比較検討1),PSPの進行に伴う経時的変化の検討2),重症筋無力症の診断3)などをおこない,臨床上非常に有用であった.
参考文献
1)市原典子,市原新一郎,藤井正吾他:videofluorographyをもちいたパーキンソン病,進行性核上性麻痺の嚥下障害の検討.臨床神経学 40:1076-1082,2000
2)市原典子,藤井正吾:進行性核上性麻痺の嚥下障害の評価と治療.神経内科56:156-163,2002
3)市原典子,石橋利行,藤井正吾他:videofluorographyが診断に有用であった重症筋無力症の1例.臨床神経学 41:367,2001